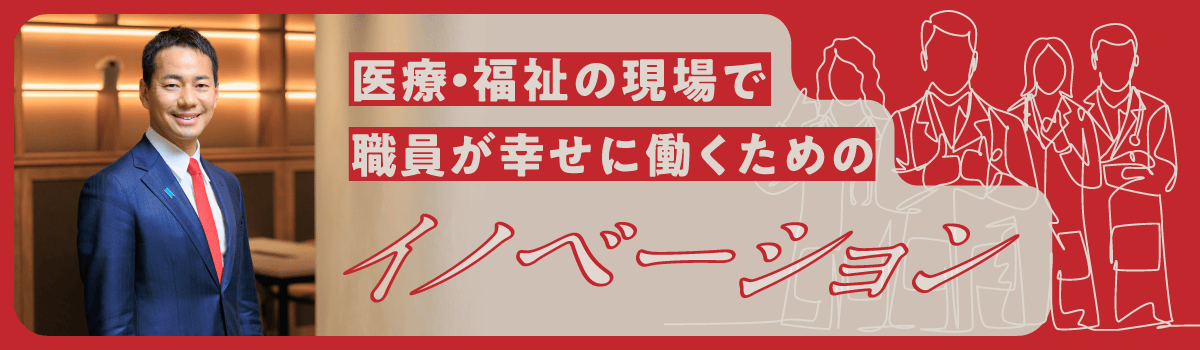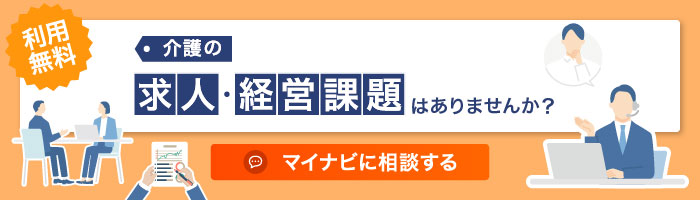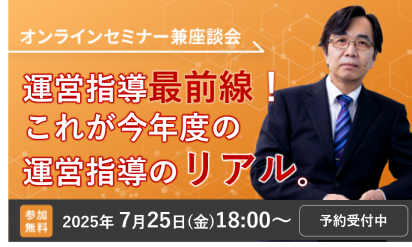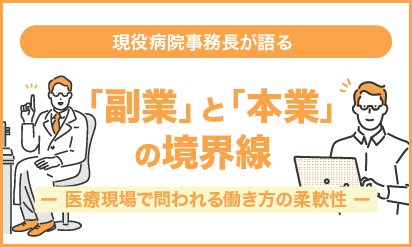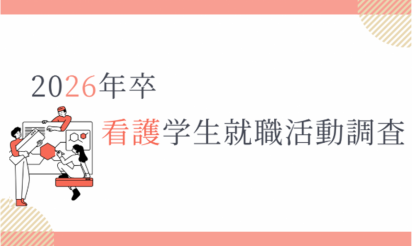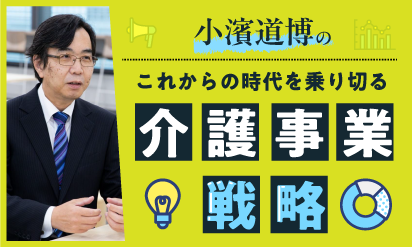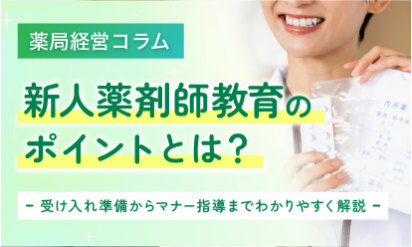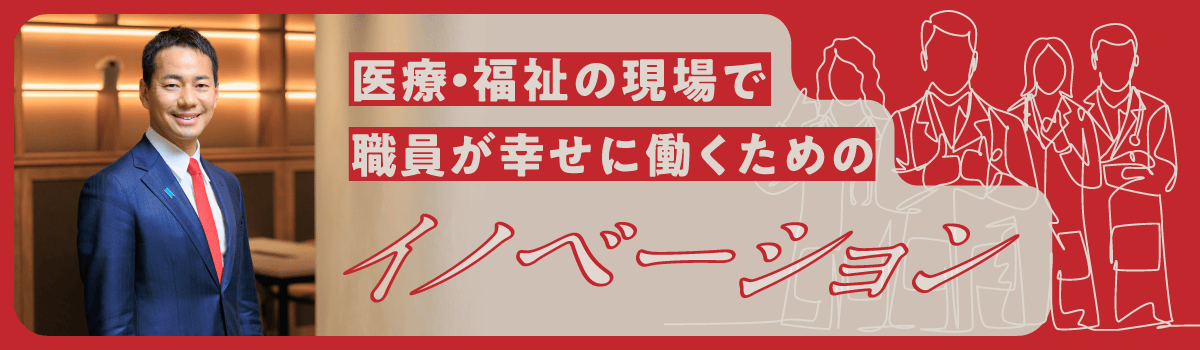
編集部より
人手不足が深刻な課題となっている医療・福祉業界で、必要な人材を獲得し、幸せに働き続けてもらうためにはどうすればよいのでしょうか。医療、社会福祉、教育と多岐にわたるサービスを提供する「さわらびグループ」のCEOである山本左近氏にお話を伺いました。日本人として最年少でF1ドライバーとしてデビュー(当時)・活躍し、その後は医療・福祉業界に転身して政治の世界にも挑んだ異色の経歴を持つ、同氏ならではの考えに迫ります。
取材・文/中澤 仁美・百谷 伶奈
編集/メディカルサポネット編集部

1. F1レーサーだからこそ強く実感した「命に向き合う仕事の重み」

私は医師である父と、社会福祉に携わる母のもとで生まれ育ちました。父は、1962年に脳卒中リハビリ病院として山本病院を開設し、その後、医療法人・社会福祉法人「さわらび会」を立ち上げ、「福祉村」の創設に着手しました。福祉村(愛知県豊橋市)とは、認知症リハビリテーションを行う療養型病院を中心に高齢者施設や障害者支援施設、就労支援のためのクリーニング工場やクッキー工房など、多様な福祉施設が集まるコミュニティです。
私は幼少期から病気や障がいを抱える方々と近しい環境で育ち、医師になることを求められる立場にありましたが、F1レーサーになる夢を諦め切れず、19歳で単身渡欧しました。それから約10年後、帰国した際に久しぶりに福祉村に戻り、多様な人々が共生するこの場所がいかに素晴らしいかを改めて強く感じました。F1レーサーとして自分の命を懸けてレースに挑戦してきたからこそ、福祉村の職員が他者の命や生活に向き合う仕事をしていることの尊さに心を打たれたのだと思います。
第二の人生の挑戦として医療・福祉の道を選び、私はまず「専門家ではない自分の役割は何だろう」と考えました。福祉村は、春になれば桜が咲き誇る緑豊かな環境にあります。ところがあるとき、理想郷のような空間に設置されたひとつの看板が、とても薄汚れていることに気がつきました。その看板には、「みんなの力で、みんなの幸せを」という福祉村の理念が掲げられていました。理念とは、企業や団体の存在理由や目的を表す大切なもの。私はバケツと雑巾を手に看板を磨き上げながら、グループとしての軸を強くすることが、この場所での最初の仕事だと覚悟したことをよく覚えています。それまでレースという厳しい競争社会で生きてきたことで、私には「何のために戦うのか」「正しいアプローチは何か」と自問自答する習慣がありました。こうした根本を捉え続ける思考法が経営にも役立つと感じました。
さわらび会に参入して5年後、私は開業55周年を見据えた「NEXT55」というビジョンを掲げ、イノベーションを起こして「超幸齢社会をデザインする」という私たちの使命を法人内で共有しました。また、「Smart Welfare Village構想」を展開し、グループ内でテクノロジーの導入を推進する方針を明確にしました。さらに、分子調理メソッドを取り入れた介護食「にぎらな寿司」の開発、画像認識技術を用いた完食率計測の実証実験など、これからの長寿社会の在り方を模索しています。F1の世界では、イノベーションの壁を突破することができず、レースから脱落していったチームをいくつも見てきました。医療・福祉業界においても旧態依然とした体制を固持するのではなく、新しいことに挑み続ける姿勢が欠かせないと感じます。
2. 人材の多様性を確保し、定着のために万事を尽くす

総務省統計局のデータによると、日本の人口が最も多かったのは2008年の1億2808万人で、その後は一転して人口減少社会に突入しています。社会が縮小していくなかで、それまでと同様に業務やサービスを展開することにこだわるから、どの業界も人手不足に陥るのだ――というのが私の考えです。医療・福祉業界でも、人材や働き方の多様性を認め、定着のために心を配る必要があるはずです。
例えば、当グループでは外国人人材の登用に力を入れています。学校法人として留学生を受け入れることに加えて、経済連携協定(EPA)に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者などの受け入れも積極的に推進。提携国であるインドネシアやフィリピン、ベトナムなどから来日する方々が専門職として働くには、日本語の習得や資格取得が必要です。そこで、外国籍の方のキャリアを支援するため、勤務時間8時間のうち2時間を勉学に充てられる制度を構築。習得が早い方では、日本語の勉強を始めてわずか2年後に、看護師国家試験に合格したケースもあります。初めは外国人と協働することに不安があった日本人職員も、彼らや彼女らが患者さんや利用者さんに優しく接していたり、資格取得に向けて努力していたりする姿を目の当たりにすることで、自然と仲間意識や応援したい気持ちが芽生えてきたようです。
離職率を下げ、人材を定着させる施策も重要です。せっかく入職してくれた人材がすぐに辞めてしまえば、採用・研修コストが無駄になってしまうからです。そこで、働きやすい職場づくりの一貫として重視してきたのが、施設内保育所の整備です。今でこそ国による幼児教育・保育の無償化が実現しつつありますが、当グループでは30年ほど前から従業員向けに保育所を無償開放してきました。産休・育休後に復職しやすいことはもちろん、すぐお子さんを送迎に行ける距離感が、職員の安心につながっていると感じます。
さらに、2017年には「SHIP(Smart Happiness Information Project)」というプロジェクトを開始。福祉村の各施設間で必要なデータをつなぎ、一括管理を実現しています。これにより患者さんや利用者さんへ、スピーディーかつスムーズなケアを提供できる上、業務を効率化することで職員の負担も軽減できるようになりました。高齢の職員でも無理なく活用できるように音声入力を可能にするなど、システム設計にはしっかりと現場の声を反映させました。導入後の研修も繰り返し行い、「このシステムを使うとこんなに仕事が楽になる」と職員に実感してもらったことが、円滑な導入につながったと思います。
3. 循環型社会の中で、医療・福祉現場の「尊厳」を守る

医療・福祉の仕事に携わる身として常々感じることは、患者さんや利用者さんの尊厳を守ることの重要性です。尊厳という言葉にはいろいろな解釈がありますが、私は「みじめな思いをしないこと」だと理解しています。現場には、「自分の態度やケアで患者さんや利用者さんにみじめな思いをさせていないか」を判断基準の一つとしながら、仕事に取り組んでほしいと伝えています。社会生活を営む上で、他人にされて嫌なことは自分もやらないのは当然のことですが、生活に密着する医療・介護の仕事では一層高い意識が求められます。定期的な利用者満足度アンケートや虐待のセルフチェックなどを含めて、当たり前に享受すべき権利を守ることができる環境を維持していきたいと思います。
また、高齢者や障害者が「常にサービスを受けるだけの存在」であることは、真に幸せな状態だとは考えていません。たとえ認知症を抱えていても、体が不自由であっても、それぞれの方ができる方法で、他者の役に立つような機会をつくることが私たちの使命です。そこで福祉村では、「循環型社会」の構築を常日頃から意識し、現場で実践しています。取り組み事例は多岐にわたりますが、例えば「看護師などの制服を、知的障害を持つ方が働くクリーニング工場で洗濯する」「老人ホームに住む方が病院を受診する際、他の利用者が車椅子を押すことを手伝う」といったことです。また、福祉村内の保育所で働く保育士は、障害のある方が描いた絵を保育所に通う子どもたちにプレゼントしたり、子どもたちがお礼に年賀状を書いたりといったタッチポイントを積極的に作り出しています。こうした関係性の連続によって信頼関係が育ち、サービスを提供する側と受ける側の垣根が低くなっていくのです。
そのほか、さわらびグループでは、サービスの質向上や業務改善を目的とした「研究発表」にも力を入れています。これは、医療や社会福祉の各分野における職員が、日々感じる業務課題に対してエビデンスベースで問題を分析し、導き出した解決策を発表する場です。グループ外部の有識者にもお越しいただき、講評を受けることも特徴の一つ。真の幸せを考えたよりよいケアの実現はもちろん、職員のやりがいの醸成にもつながっていると感じ、今後も継続していきたいと考えています。
4. 官民一体となり、今こそ医療・福祉業界にも改革を

医療・福祉業界は人材不足という明確な課題を抱えており、政策としても需給バランスを是正する必要があります。2024年度の報酬改定では診療報酬+0.88%、介護報酬+1.59%実現されましたが、昨今の物価高を考えると十分とは言えません。これだけで職員の処遇改善や人材確保につなげるのは難しいでしょう。医療・介護は人手が必要な労働集約型の産業であり、介護施設の種類や運営形態による違いはあっても、経費のおおむね6〜7割が人件費となります。日本全国に存在する医療法人や社会福祉法人が捻出する経費のうち、約5〜7割が個人の給与として国内で循環していくことを考えても、物価にスライドさせるなど、報酬改定率のさらなる上昇が実現されるべきだと考えます。
また、人員配置基準の見直しも要検討でしょう。医療・福祉業界の人員配置基準は、安全で適切なサービスを提供するために、国が定める最低限の職員配置ルールです。しかし、これからも人手不足が加速していくことを考えれば、1人の職員が担当できる人数を増やすためにイノベーションを促進していくことは不可欠です。その一例として、厚生労働省では2024年にヘルスケア分野のスタートアップ支援を強化する取り組みが始まり、「ヘルスケアスタートアップ等の振興・支援策検討プロジェクトチーム」が設立されています。
今後、人材不足の解消や介護負担の軽減をめざして、これまで人が行っていた業務をツールやシステムで代行する動きはますます加速していくでしょう。ここで重要なのは、DX化を推進する医療・福祉事業者のインセンティブを用意することです。せっかくコストをかけて新たなツールやシステムを導入し、人員配置基準が0.1削減されたところで生身の人間を分割できるわけではありません。この政策の更なる推進のためには少なくとも初期段階では事業者に経済的なメリットが必要です。
時間稼ぎをするような施策ではなく、より大局的な視点で制度改正を検討する必要があります。各省庁と現場で力を尽くす私たち民間事業者が一丸となって議論を深めながら、業界として進むべき未来を選択する時期が訪れていると、いま強く感じています。
プロフィール
山本左近(やまもと さこん)
自由民主党 前衆議院議員
幼少期に見たF1日本GPでのセナの走りに心を奪われ、将来F1パイロットになると誓う。両親に土下座して説得し、1994年よりカートからレーシングキャリアをスタートさせる。2002年より単身渡欧。ドイツ、イギリス、スペインに拠点を構え、約10年間、世界中を転戦。2006年、当時日本人最年少F1デビュー。2012年に日本に拠点を移し、ホームヘルパー2級を取得し、医療法人/社会福祉法人の統括本部長として地域の医療福祉に邁進。2018年、学校法人を含む、医療・福祉・教育の3本柱となった、さわらびグループのCEO/DEOに就任。
2019年7月 第25回参議院議員通常選挙(比例代表)に自民党公認で立候補し、78,236票を獲得するも落選。
2021年10月第49回衆議院議員総選挙自民党比例代表(東海ブロック)初当選。
当選直後から、合成燃料の国産化の必要性を訴え、日本初の実証プラントの稼動を実現した。
また、2022年8月、初当選後一年に満たない中、文部科学大臣政務官 兼 復興大臣政務官に異例の抜擢。
在任中、大型放射光施設SPring-8の高度化プロジェクトを座長として取りまとめた。またアニメ等のコンテンツ産業の人材育成支援のプロジェクトを推進し、大型基金の獲得への筋道をつけるなど活躍。
2024年10月第50回衆議院議員総選挙自民党比例代表で2期目に立候補するも落選し現在に至る。
日本語、英語、スペイン語を話すマルチリンガル。