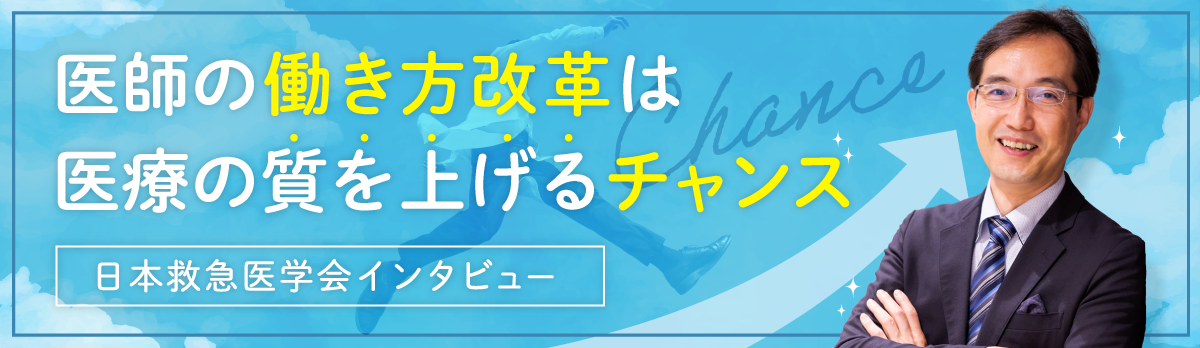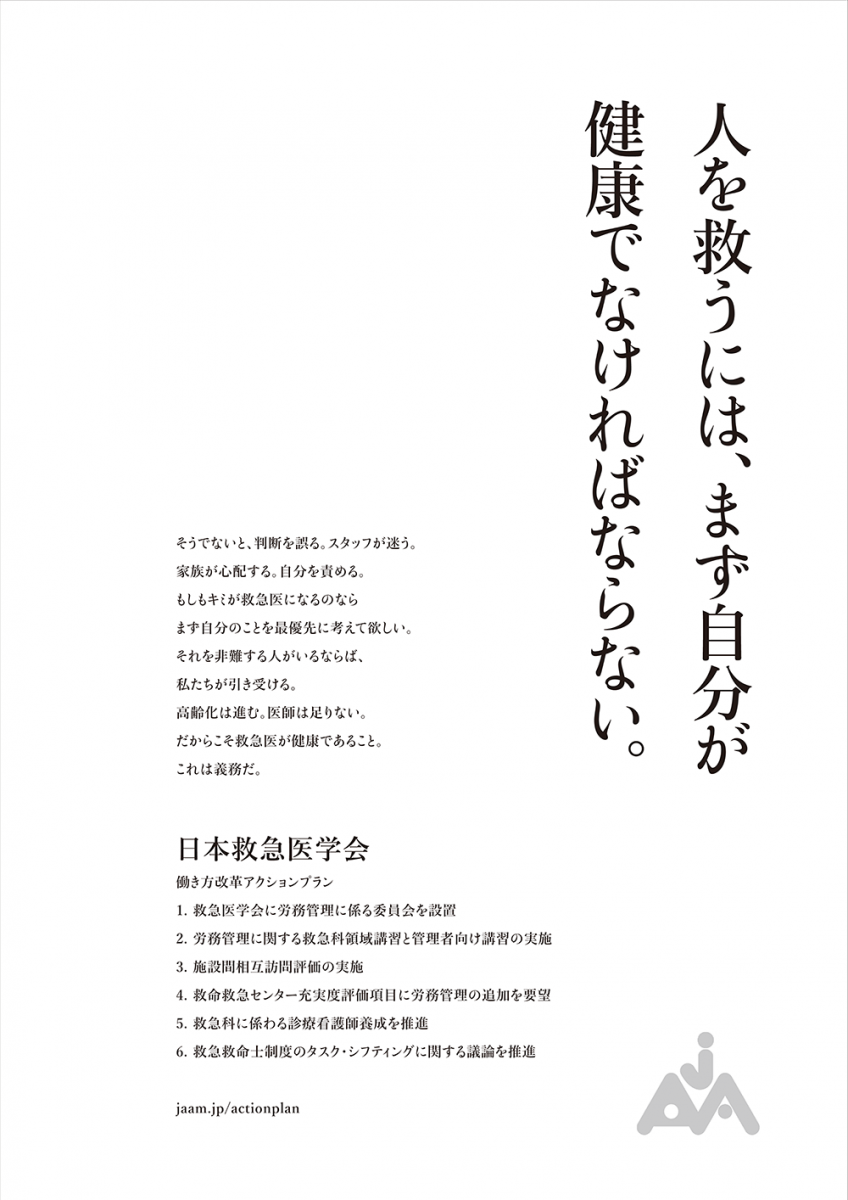関連記事一覧

攻めの中小病院経営 ~事務部門が動かすヒト・モノ・情報~vol.10
組織の価値向上につながる医師会活動
~断らない姿勢で、情報が集まり、人との交流が増える病院へ~
~断らない姿勢で、情報が集まり、人との交流が増える病院へ~
★
★
★
★
★
5

へき地等で医師常勤不要の専用診療所を容認へ―オンライン診療の場所拡大で厚労省
★
★
★
★
★
3

時間外労働等が年1860時間超の大学病院勤務医は2.4%-働き方改革準備状況調査
★
★
★
★
★
3
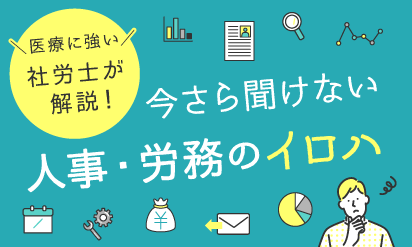
今さら聞けない人事・労務のイロハ vol.2
どう管理する?医療従事者の労働時間
★
★
★
★
★
5

働き方改革で病院長向け研修、事例を共有
初回28日、事務長らの同席も可能 厚労省
初回28日、事務長らの同席も可能 厚労省
★
★
★
★
★
5
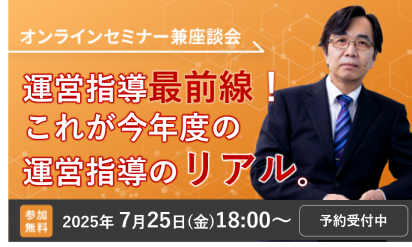
【7/25開催オンラインセミナー】
運営指導最前線!これが今年度の運営指導のリアル。
運営指導最前線!これが今年度の運営指導のリアル。
★
★
★
★
★
5