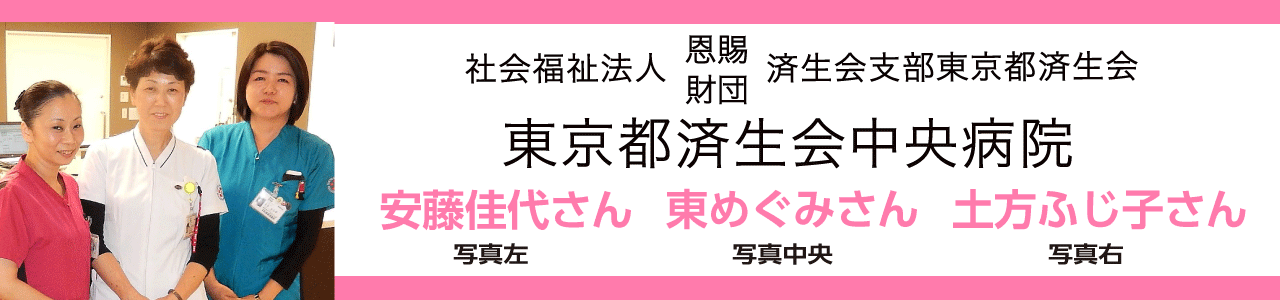関連記事一覧

「4月に入職してきたばかりの看護師から、もう退職したいと相談があった…」そんなお悩みを抱えていませんか?
【期間限定アーカイブ配信】アンケートから見えた現場の本音。人材育成のスペシャリストが採用成功と効果的な人材育成方法を解説!
★
★
★
★
★
5
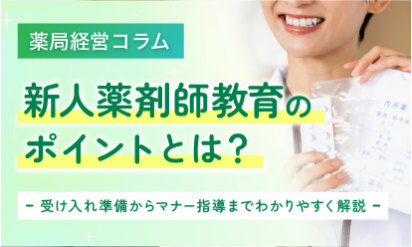
新人薬剤師教育のポイントとは?受け入れ準備からマナー指導までわかりやすく解説
★
★
★
★
★
5

~菊地雅洋の一心精進・激動時代の介護経営~Vol.7
骨太の方針2025に明記された介護報酬引き上げ方針を読み解く
★
★
★
★
★
5
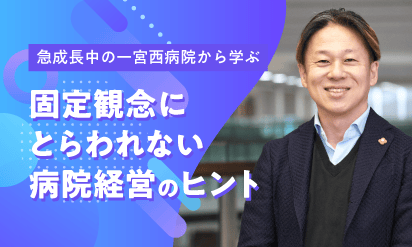
一宮西病院事務長・前田昌亮さんスペシャルインタビュー
急成長中の一宮西病院から学ぶ、固定観念にとらわれない病院経営のヒント
★
★
★
★
★
5
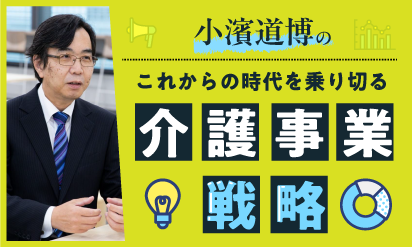
~小濱道博のこれからの時代を乗り切る介護事業戦略 vol.7~
令和6年度介護職員等処遇改善加算等実績報告書作成ガイド
★
★
★
★
★
5

現場で役立つ!看護マネジメント入門
第4回 組織論 ―ピラミッド型とチーム型の使い分け―
★
★
★
★
★
5