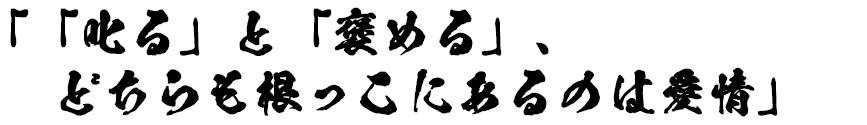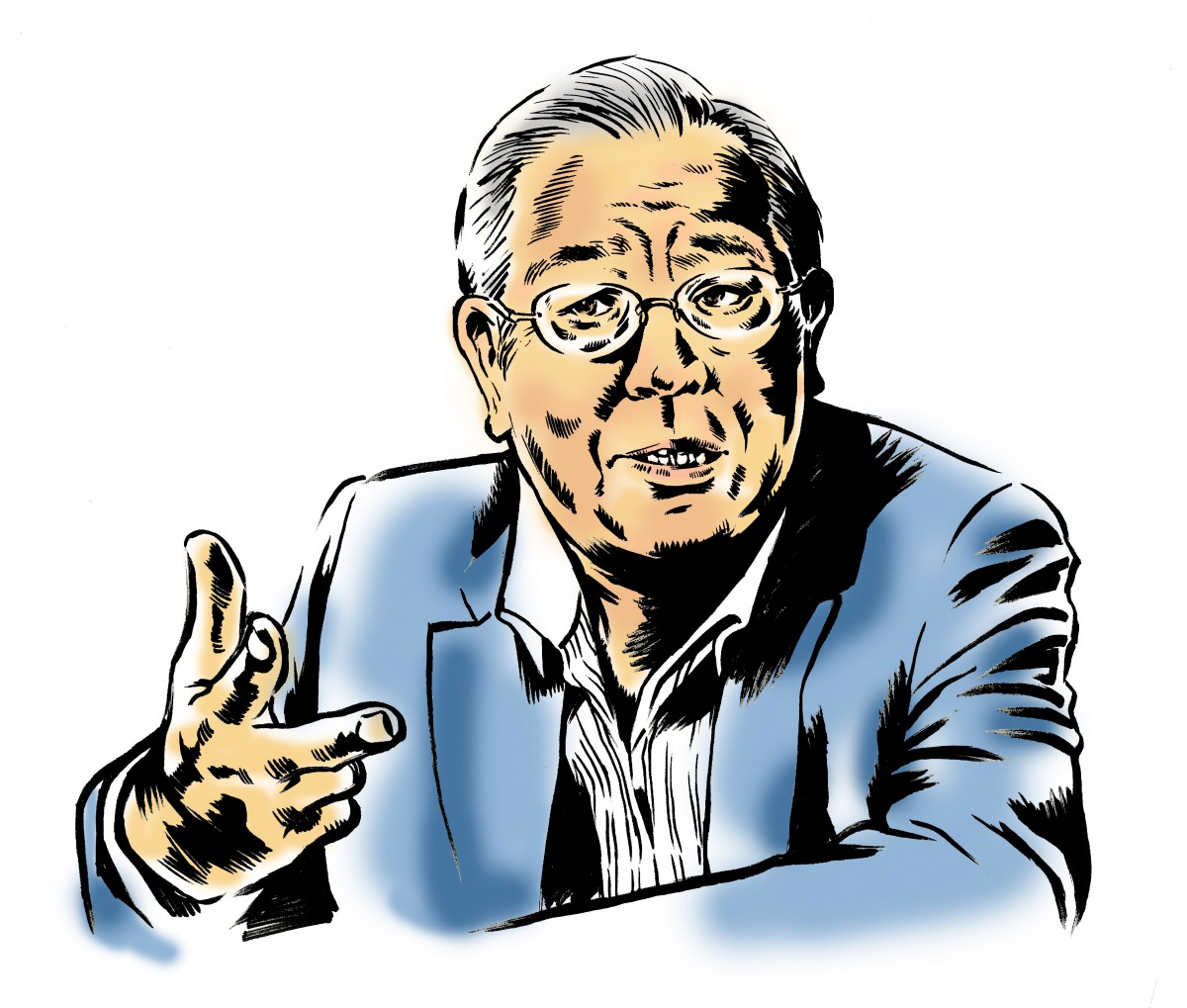関連記事一覧
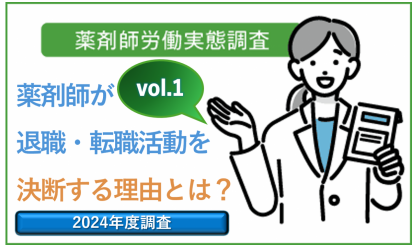
5分で読めるポイント解説 薬剤師白書2024
vol.1 薬剤師が退職・転職活動を決意する理由とは?
★
★
★
★
★
5
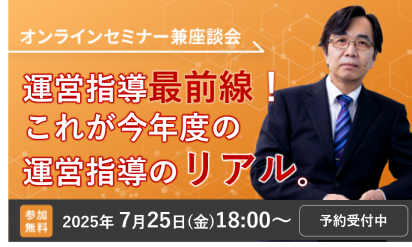
【7/25開催オンラインセミナー】
運営指導最前線!これが今年度の運営指導のリアル。
運営指導最前線!これが今年度の運営指導のリアル。
★
★
★
★
★
5
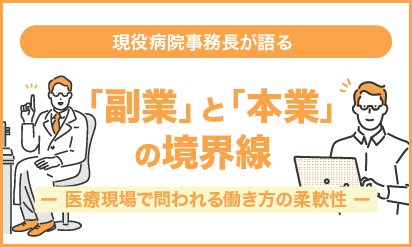
現役病院事務長が語る
「副業」と「本業」の境界線 ─医療現場で問われる働き方の柔軟性
「副業」と「本業」の境界線 ─医療現場で問われる働き方の柔軟性
★
★
★
★
★
5
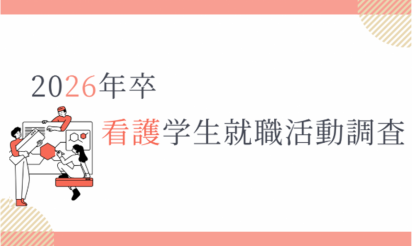
◆資料ダウンロード◆2026年卒 看護学生就職活動意識調査(2025年3月・4月実施)
2026年卒 看護学生就職活動意識調査(3月・4月)
★
★
★
★
★
5
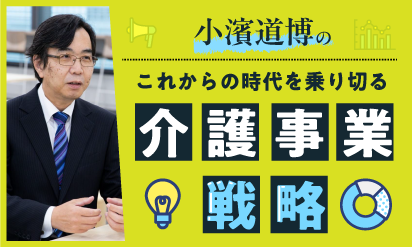
~小濱道博のこれからの時代を乗り切る介護事業戦略 vol.8~
訪問介護における外国人材導入の現状と課題
★
★
★
★
★
5

「4月に入職してきたばかりの看護師から、もう退職したいと相談があった…」そんなお悩みを抱えていませんか?
【期間限定アーカイブ配信】アンケートから見えた現場の本音。人材育成のスペシャリストが採用成功と効果的な人材育成方法を解説!
★
★
★
★
★
5