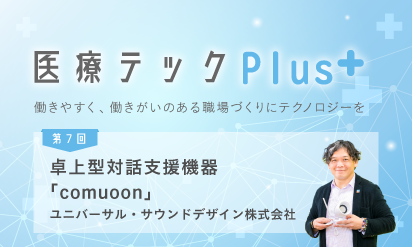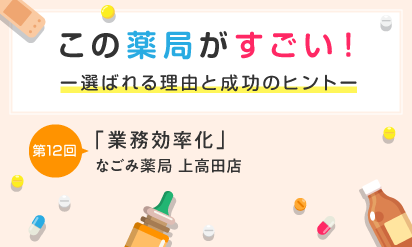震災で決意 「医療者を救うことが、医療を救う」
前職では医療系のアプリの開発などに携わってきた峯さんが独立し、ハードウェアの制作を手掛けるまでにはさまざまな経緯があったそう。最も大きかったのは、2011年の東日本大震災でした。
――シェアメディカルを立ち上げるまでには、さまざまなお仕事をなさっていたのですね。
峯啓真さん(以下、峯):はい。かなり前のことになりますが、デザイナーもしていました。医療に関心を持ったのはその頃です。アロマテラピー製品のパッケージをデザインしたとき、その効能について調べたんです。「リラックス効果」といったものがどんなメカニズムで生じるのかが分かり、「人体って面白いな!」と思いました。もともと理系だったこともあり、医療に興味が湧いたんですね。そこから医療情報を扱うメディア企業に転職し、サービスの開発を手掛けるようになりました。当初は病院の口コミサイトなどをつくっていましたが、スマートフォンが登場すると、アプリの開発が主な仕事になっていきました。

「デザイナー時代に医療に興味を持ち、医療者向けアプリの開発を始めた」と話す株式会社シェアメディカル代表取締役の峯啓真さん
――当時手がけていたのは患者向けのサービスですか?
峯:そうですね。病院や薬の検索といった患者さんをサポートするためのアプリやサービスの開発が中心でした。4年くらいした後、医師や医療関係者向けのアプリ開発にも進出しました。そうなると、医師という人々について知らなければなりません。彼ら彼女らが何に悩み、何に苦しみ、どんなものを欲しいと思っているのかを調べる必要があったのです。すると、いろいろな課題が見えてきて、彼らの多大な献身の上に今の日本の医療産業があると改めて分かりました。よくも悪くも「医は仁術」という言葉に縛られていました。ただ、そういう誰かが無理をすることで成り立っている産業は、いつ崩壊してもおかしくない。「彼らを救うことこそが医療を救うことなんだ」と思うようになりました。
――そんな中で東日本大震災が起きた…。
峯:震災にはショックを受けましたね。なぜなら、通信回線が使えなくなってしまったとき、自分がつくってきたサービスは一切機能しなくなったからです。「なんて無力なのか…」と感じました。その事実に打ちひしがれて、しばらく仕事が手につかなくなり、そのとき進めていた開発はすべてストップして、もう一度コンセプトから考え直すことにしました。そんなとき、津波でびしょ濡れになった段ボール箱からカルテを取り出し、ガラスに貼り付けて乾かし、診療を再開しようとしている医師の姿をテレビで観ました。その姿に「本当にすごい人たちだな」と胸を打たれたのです。「テクノロジーを使って、真の意味で彼らのためになることをしたい」と思いました。
医療現場のリアルな声からニーズを探る
震災をきっかけに、医療への貢献をより強く願うようになった峯さんは独立を決意。2014年にシェアメディカルを設立します。独立して最初に手掛けたのは、自らが得意とするアプリの開発でした。
峯:震災後は、とにかく医師たちが考えていることやメンタリティをもっと深く知りたいと思い、SNSなどで数千人の医師をフォローして観察しました。時には会いに行って実際にお話を聞くことも繰り返しました。そこでいろいろな情報を得たことが、独立に向けた準備になりましたね。その後、震災から時間が経っているのに状況がなかなか好転しないことも独立を後押ししたように思います。「3年経ったのに何も変わらないじゃないか」と苛立ちを感じたのです。
 「テクノロジーを使い、真の意味で医療者のためになることをしたいと思った」と振り返る峯さん
「テクノロジーを使い、真の意味で医療者のためになることをしたいと思った」と振り返る峯さん
――シェアメディカルとして最初に開発したのが医療・介護用メッセージングツール「MediLine(メディライン)」でした。
峯:「メディライン」は、コミュニケーションアプリ「LINE」の医療関係者用のようなものです。独立を決意して前職を辞めた後、医療機関でインターンをさせてもらうなどして、より深く現場を学んだのですが、コミュニケーションの効率の悪さが目に付いたんです。医療現場では、さまざまな職種の人たちが連携していて、看護師などは交代制で引き継ぎ事項も多い。ただでさえコミュニケーションが大事な環境なのに、多忙な医師に対してコミュニケーションを取ることをスタッフが遠慮するという問題点もあり、停滞を招いていました。「そういう人たちがスムーズに情報を交換できるツールが求められているはずだ」と考えて生まれたのが、「メディライン」だったというわけです。
――その後、いくつかのアプリ開発を経て、初のハードウェアとして「Nexthetho(ネクステート)」の開発に取り組まれたのですね。聴診器が長らく変化せず、デジタル化がなされていなかったことには驚かされました。
峯:本当にそうですよね。素材などは変わっていますが、基本的な構造は200年変わっていないんです。医療の世界とそれなりに長く関わっていた私も知りませんでした。ある医師が「学校検診で1日に何百人も聴診したから耳が痛いよ。あれ、なんとかならないのかな? 21世紀だっていうのにね」と笑いながら話したんです。それをきっかけに聴診器について詳しく調べ、歴史を知りました。耳が痛くなることも「そういうものだ」とされてきて、医師から表立った不満は出てこなかったのでしょう。先ほども言ったように、私は「医師たちの悩みや困りごとを解決し、救いたい」という思いを抱いて独立していますから、ぜひなんとかしたいと思いました。
 聴診器デジタル化ユニット「ネクステート」を付けた聴診器。チェストピースのチューブと連結する部分に装着する
聴診器デジタル化ユニット「ネクステート」を付けた聴診器。チェストピースのチューブと連結する部分に装着する
――なるほど。そうした経緯を経て開発した「ネクステート」の構造について教えてください。
峯:聴診器は、チェストピースと呼ばれる患者さんの胸部などに当てる丸い金属できた部分で音を拾い、それをチューブ、金属でできた耳管、樹脂製のイヤーピースを通して鼓膜に届けています。イヤーピースは耳の奥まで挿し込まないと音がよく聞き取れないため、バネを使って押し付けるのです。長時間付け外しを繰り返していると、耳が痛くなってしまいます。「あれは拷問器具だ」と笑い話をする医師もいました。「ネクステート」は、チェストピースのチューブと連結する部分に装着する装置で、チェストピースで拾った生体音をセンサーで拾い、デジタル化するものです。デジタル化した音ならば、大きくしたり鮮明にしたり、Bluetoothで飛ばしたりすることができるので、私たちが音楽を聴くときに使うようなヘッドフォンでしっかり聴き取れます。耳の奥まで挿し込まないといけないイヤーピースが必要なくなるのです。

「ネクステート」を装着した聴診器でデジタル化した心音を自ら聞く峯さん。イヤホンは手持ちのものを使用
――開発はスムーズにいったのですか?
峯:最初は自作も検討したのですが、一筋縄ではいかず…。志を共有できる企業を探し回りました。テレビドラマの「下町ロケット」みたいな出会いを期待したんですが、実際は簡単じゃなかったですね(笑)。ところが、台湾のものづくり企業と日本のベンチャー企業をつなぐイベントに足を運んだとき、興味を持ってくれる人が現れたんです。聞けば、元々ソニーで「ウォークマン」の開発に携わった人で、「あらゆる音をデジタル化したと思っていましたが、まだデジタル化されていない分野が残っていたんですね。ぜひ一緒にやりましょう」と言ってくれました。実現できるメーカーとも出会い、開発がスタートしました。
高齢医師の支援や教育への活用にも期待
台湾のオーディオメーカーと力を合わせ、「聴診器の再発明」に取り組むようになった峯さん。当初は「目の前の医師の悩みを解消したい」というシンプルな思いで始まったプロジェクトでしたが、実際に製品が完成すると大きな反響があり、一気に視界がひらけたそうです。
峯:ハードウェアを手掛けるとなると、開発だけでなく材料を仕入れたり生産にも費用がかかったりし、売れなければ在庫を抱えねばならず、ソフトウェア開発と比べてリスクがあります。ベンチャー企業に向いている分野とはいえず、事実、投資家からは懸念する声もありました。でも私はもともとアプリ開発を長くやっていて、「まずはつくってみて、さまざまな声を取り入れて改善していけばいい」と考えています。だからあまり臆せず、「開発費がトントンならいいかな」くらいの気持ちで踏み出したのです(笑)。でも、それがよかった。実際にモノをつくってみると、いろいろなことが見えてきて、周囲の医療に関わる人々も想像以上の反応を示してくれたからです。
――具体的にはどんな反響があったのですか?
峯:まず、年配の医師たちから反響がありました。加齢に伴い聴力が低下し、聴診器で心音が聞き取りづらいという悩みが解消できたという喜びの声をいただきました。また、これまで聴診器の音は、耳に当てている医師しか聞けなかったものですが、「ネクステート」で音をデジタル化することによって誰もが聞こえるものになりました。「カンファレンスで研修医に聞かせながら勉強会をしたい」という声も相次ぎました。訪問看護に従事している方からの反響も大きいですね。聴診した結果を医師と共有し、相談ができる点にメリットを感じてもらっているようです。お父さんやお母さんに子どもの心音を聞かせてあげることで、安心させる小児科の先生もいました。それ以外にも、「音声データを集めて人工知能に学習させれば、自動診断への道が開けるはずだ」というアドバイスも届きました。
――まさに「ネクステート」が起こした、イノベーションと呼ぶべき反響ですね。
峯:そうですね、細かなこだわりですが、私としてはイノベーション(技術革新)というよりは、あくまでデジタリゼーション(デジタル化)ではないかと考えています。「ネクステート」をまったく新しい聴診器の形にせず、既存の聴診器に組み込むスタイルにしたのは、既存の医療の守るべき部分を守りながら、よりよくしたいと思ったことも理由の一つです。医師に聴診器という馴染みのある器具を使って診察されることで、それだけでほっとする患者さんも多くいるわけです。その関係性を壊したくないという思いもあったんです。

年配の医師に喜ばれたり、カンファレンスで音を聞きながら勉強会をしたいと言われたり。反響は大きい。
――現状の医療に対するリスペクトも強くお持ちですね。今後の展開に関し、何か計画はありますか?
峯:デジタリゼーションに成功した「ネクステート」は一定数売れると思いますが、それでは面白くない。私は「ユビキタスヘルスケア」と言っているのですが、必要な医療を必要な人に届ける「ネクステート」をコアにして、今までできなかった遠隔聴診など次世代の遠隔医療の充実に寄与していきたいと思っています。また、デジタル化することで、データがどんどん蓄積できるようになります。もしかしたら、人間の耳で聞き取れない音を人体は発しているかもしれません。データを蓄積していれば鋭敏なセンサーとAIが後々新しい診断方法を見つけるかもしれません。そして、本当に医療を必要としている海外への展開も見据えています。まずは国内でそうした遠隔医療に懐疑的な人たちに納得していただくために、データを提示して納得してもらう。「聴診もできない」と批判するのなら、遠隔聴診を可能にしてしまう。対面医療とほぼ同じようなレベルにすることで、批判の声を封じ、応援してくれる人がどんどん増えれば、最終的には聴診そのものの役割と位置づけが変わっていく。それが、医療版の「デジタルトランスフォーメーション(DX)」の始まりではないかと思うのです。その先にイノベーションと呼べる未来が見えてきます。それを実現するのがテクノロジストとしての私の役割だと思っています。
医療に携わる人への尊敬と、ダイナミックな変革のために“突っ走る”熱量。その両方を兼ね備えた峯さんだからこそ切り拓ける未来。“(勢いで)つくってしまった”と笑う「ネクステート」の向こうに、それが見えた気がしました。
株式会社シェアメディカル
住所:東京都千代田区大手町1丁目6−1 大手町ビル 2F SPACES
URL:https://www.sharemedical.jp/
峯啓真代表取締役・CEOが2014年9月1日に設立。医療・介護用メッセージングツール「MediLine(メディライン)」や医療辞書搭載API組込型翻訳サービス「医詞(いことば)」などモバイルアプリを開発。2018年、約200年間進化のなかった聴診器のデジタル化ユニット「Nexthetho(ネクステート)」の開発に取り組み、19年12月から発売。聴力が低下した高齢の医師が長く現場で活躍できる環境づくりや、「聴診音」共有の実現による実務医学教育の変革など多方面から期待を集めている。
メディカルサポネット編集部(取材日/2020年1月27日)

↑back number はこちらをクリック↑
BACK NEXT