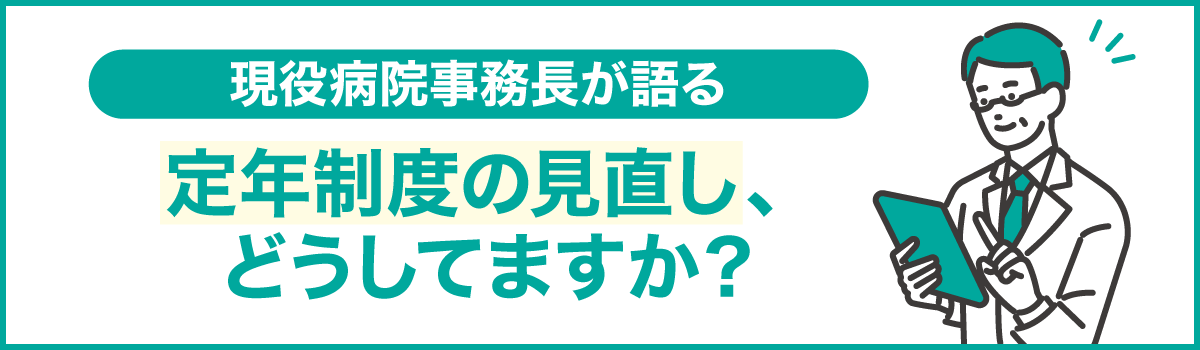関連記事一覧
_w412px_h247px.png)
◆資料ダウンロード◆マイナビ独自調査【看護師白書2024年度版】
看護師2564人のリアル 労働・雇用実態調査
『看護師白書2024年度版』~看護師の「労働実態」「就業・転職志向」とは?~
『看護師白書2024年度版』~看護師の「労働実態」「就業・転職志向」とは?~
★
★
★
★
★
5
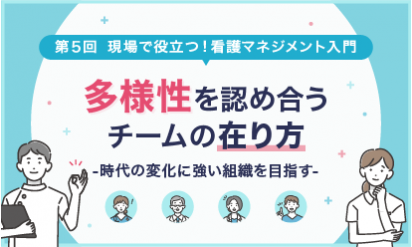
現場で役立つ!看護マネジメント入門
第5回 多様性を認め合うチームの在り方
―時代の変化に強い組織をめざす―
―時代の変化に強い組織をめざす―
★
★
★
★
★
5
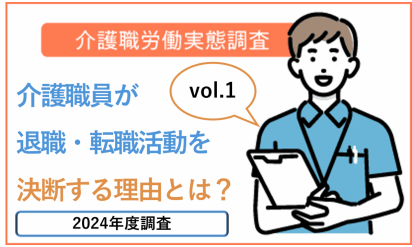
5分で読めるポイント解説 介護職白書2024
vol.1 介護職員が退職・転職活動を決意する理由とは?
★
★
★
★
★
5
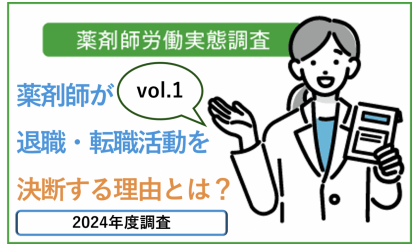
5分で読めるポイント解説 薬剤師白書2024
vol.1 薬剤師が退職・転職活動を決意する理由とは?
★
★
★
★
★
5
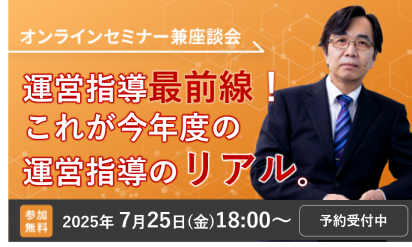
【7/25開催オンラインセミナー】
運営指導最前線!これが今年度の運営指導のリアル。
運営指導最前線!これが今年度の運営指導のリアル。
★
★
★
★
★
5
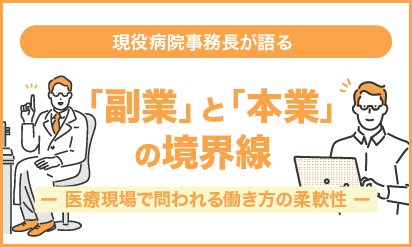
現役病院事務長が語る
「副業」と「本業」の境界線 ─医療現場で問われる働き方の柔軟性
「副業」と「本業」の境界線 ─医療現場で問われる働き方の柔軟性
★
★
★
★
★
5