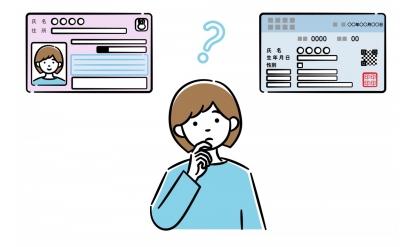メディカルサポネット 編集部からのコメント今や100均でもダイエット・サプリが販売されています。プライベート・トレーニングのジムも盛んです。体型をキープするためには、食事と運動の併用が必要だとはわかっています。しかし、誰もが強い意志でセルフコントロールができるわけではありません。とはいえ「抗肥満薬を飲めば痩せるから、また太っても大丈夫」と認識されてしまっては本末転倒です。なぜ食べてしまうのか、時間を忘れて熱中できるものはないのか、原因を探るためにも、診察時間中にどれだけ患者が心を開けるか……医師の話術の発揮どころです。 |
国内外の肥満薬物治療の現状および進歩についてご教示下さい。岩手医科大学・石垣 泰先生のご回答をお願いします。
【質問者】
龍野一郎 日本肥満症治療学会理事長/東邦大学医療センター佐倉病院内科学講座 主任教授
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
【回答】
| 【体重減少が期待できる糖尿病治療薬が出てきている】 |
肥満症治療の基本は,食事・運動療法を中心にした生活習慣の改善です。肥満者の生活習慣は変えられないことも多いのですが,他の生活習慣病と違って肥満症には適応となる薬剤がほとんどなく,治療に苦慮することが多い分野です。
マジンドールはわが国で唯一使用可能な抗肥満薬です。中枢におけるノルアドレナリンの再取り込み阻害薬で,食欲中枢の抑制と満腹中枢の促進作用によって食欲を抑制します。日本人を対象にした試験では,3カ月間の投与で平均4.2kgの体重減少が得られており,症例によっては10kg以上減量する人もいます。しかし,口渇や便秘,悪心といった副作用がみられ,また精神障害を有する患者には投与禁忌となっています。依存性に注意が必要なことから,2週間処方で期間も3カ月間に限定されており,BMI 35以上の高度肥満にしか適応が認められていないなど,処方しにくい印象は否めません。3カ月の処方期間が終了した後にリバウンドする患者が多いことも問題です。
世界ではいくつかの中枢性食欲抑制薬が使用されています。セロトニン受容体アゴニストであるlorcaserinは選択性が高く副作用が少ないため,米国を中心に評価が定着しています。しかし一方で,わが国でも第3相臨床試験までいったセロトニン・ノルアドレナリン取り込み阻害薬であるsibutramineは頻脈や血圧上昇のため,カンナビノイド阻害薬であるrimonabantはうつ症状増悪のため,いずれも開発中止となっています。
他の作用機序による抗肥満薬として,腸管からの吸収阻害薬があります。減量効果は大きくないものの,血糖,血圧,脂質といった代謝異常が総合的に改善するという長所があります。また下痢や脂肪便といった副作用があるものの重篤ではなく,米国ではover the counter(OTC)医薬品として広まっています。
最近では体重減少が期待できる糖尿病治療薬が出てきています。グルカゴン様ペプチド(glucagon-like peptide-1:GLP-1)受容体作動薬は胃腸の蠕動運動抑制を介して,また一部は,中枢性の食欲抑制作用によって体重が減少します。わが国でも使用されているリラグルチドの3倍以上の用量(3.0mg/日)の製剤が,米国で抗肥満薬として認可されています。また,わが国でも発売予定のセマグルチドは,週1回投与で良好な減量効果が得られると報告されています。sodium-dependent glucose transporter(SGLT)2阻害薬は,尿中に糖を排泄することでエネルギーバランスを負に傾け,体重減少が得られる薬剤です。血糖や体重への効果のほかに,心血管イベント抑制や腎保護作用が注目されています。ただし,薬剤投与で食欲が増す可能性があるため食事療法の徹底が必要です。
肥満者に併発する健康障害の多くは体重減少によって改善がみられますが,生活習慣の改善が難しい患者や改善しても体重が減らない患者も存在します。こうした例には肥満薬物療法が適応になると思われますが,抗肥満薬を長期にわたって投与するのではなく,薬剤の補助によって減量の成功体験を得て,そのことを肥満症治療のモチベーションにつなげることが薬物治療の目的と考えます。
【回答者】
石垣 泰 岩手医科大学医学部内科学講座糖尿病・代謝・内分泌内科教授
執筆:
龍野一郎 (日本肥満症治療学会理事長/東邦大学医療センター佐倉病院内科学講座 主任教授)
石垣 泰 (岩手医科大学医学部内科学講座糖尿病・代謝・内分泌内科教授)
出典:Web医事新報