関連記事一覧
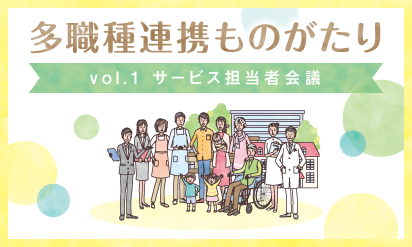
多職種連携ものがたり vol.1
サービス担当者会議
★
★
★
★
★
5

そこが知りたい看護管理 <インタビュー編>
元看護管理者 森田夏代さんインタビュー
★
★
★
★
★
5

看護部ビフォーアフターvol.1
社会医療法人至仁会 圏央所沢病院
★
★
★
★
★
5

+αで活躍する医療従事者 vol.2
中尾 妙さん(看護師+クラシコ株式会社商品企画)
★
★
★
★
★
5

【 医療テックPlus+】
第5回/トリプル・ダブリュー・ジャパン株式会社
排尿リズムを可視化 個別ケアを可能に(DFree)
★
★
★
★
★
5
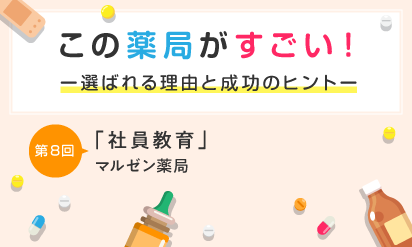
この薬局がすごい! 第8回「社員教育」
主体性を尊重 業務提案や勉強会が盛んに
(マルゼン薬局)
(マルゼン薬局)
★
★
★
★
★
5


