関連記事一覧
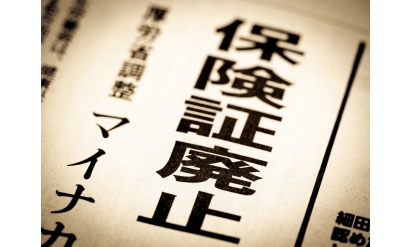
1700万人の保険証が7月末に期限切れ─厚労省、国保加入者に確認呼びかけ
★
★
★
★
★
3

機能分化・連携の前に入院基本料引上げや人員基準緩和を─中医協総会で診療側
★
★
★
★
★
3

「ALP」の普及へ東大でシンポジウム開催 自分らしい老後を実現する新たな備えのプロセスを考える
★
★
★
★
★
3
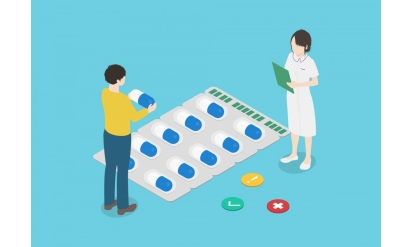
退院時の処方漏れによる内服の中断で注意を喚起―医療安全情報
★
★
★
★
★
3

SOMPOケアの子ども食堂、提供5万食突破 地域の子どもの成長を支え、高齢者は笑顔に
★
★
★
★
★
3

訪問介護+通所介護の新サービス創設を 介人研が要望書 報酬の引き上げ・処遇改善も
★
★
★
★
★
3

