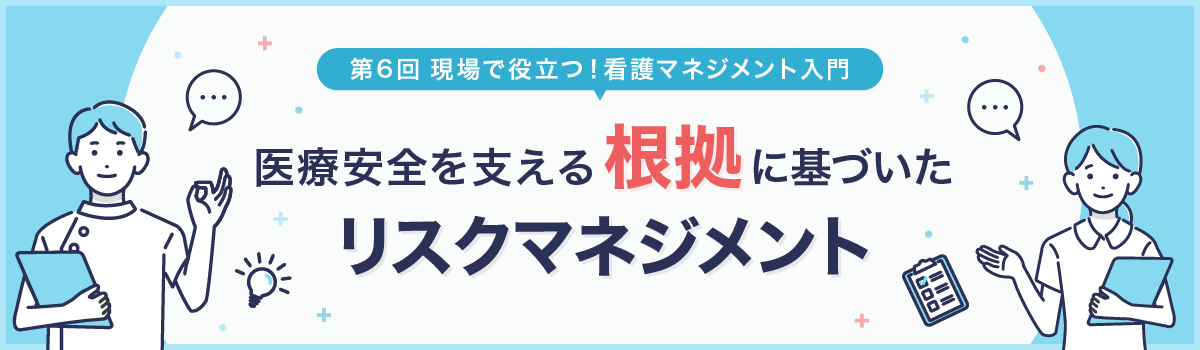関連記事一覧
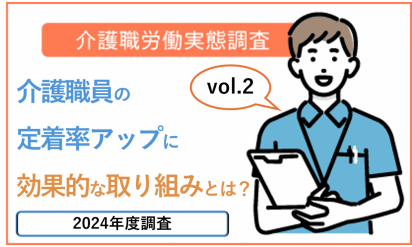
5分で読めるポイント解説 介護職白書2024
vol.2 介護職員の定着率アップに効果的な取り組みとは?
★
★
★
★
★
5
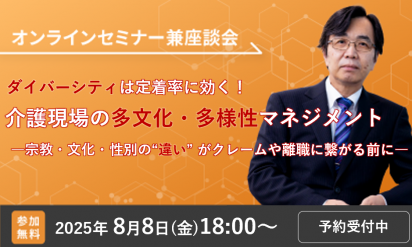
【8/8開催オンラインセミナー】
ダイバーシティは定着率に効く!
介護現場の多文化・多様性マネジメント
―宗教・文化・性別の“違い”がクレームや離職に繋がる前に―
ダイバーシティは定着率に効く!
介護現場の多文化・多様性マネジメント
―宗教・文化・性別の“違い”がクレームや離職に繋がる前に―
★
★
★
★
★
5
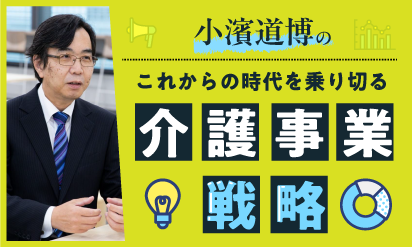
~小濱道博のこれからの時代を乗り切る介護事業戦略 vol.9~
骨太の方針2025を読み解く
★
★
★
★
★
5
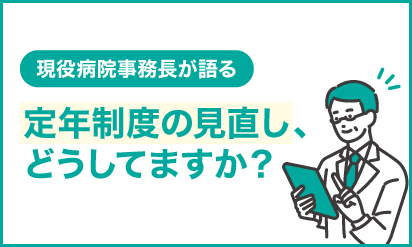
現役病院事務長が語る
定年制度の見直し、どうしてますか?
定年制度の見直し、どうしてますか?
★
★
★
★
★
5
_w412px_h247px.png)
◆資料ダウンロード◆マイナビ独自調査【看護師白書2024年度版】
看護師2564人のリアル 労働・雇用実態調査
『看護師白書2024年度版』~看護師の「労働実態」「就業・転職志向」とは?~
『看護師白書2024年度版』~看護師の「労働実態」「就業・転職志向」とは?~
★
★
★
★
★
5
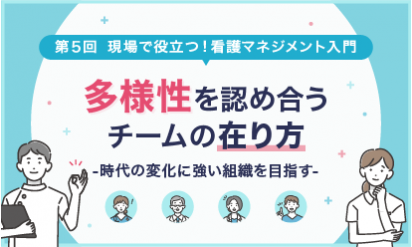
現場で役立つ!看護マネジメント入門
第5回 多様性を認め合うチームの在り方
―時代の変化に強い組織をめざす―
―時代の変化に強い組織をめざす―
★
★
★
★
★
5